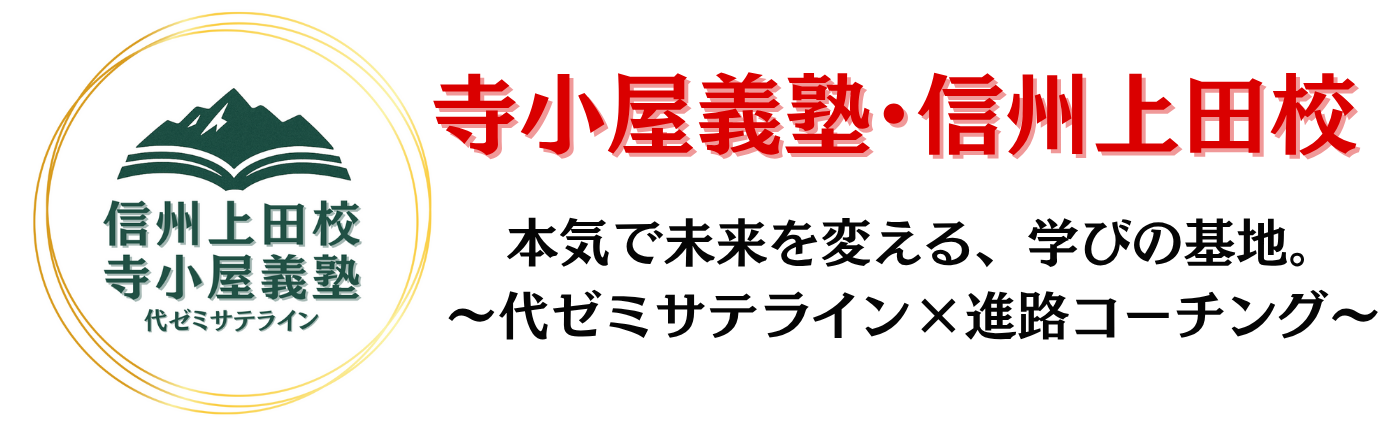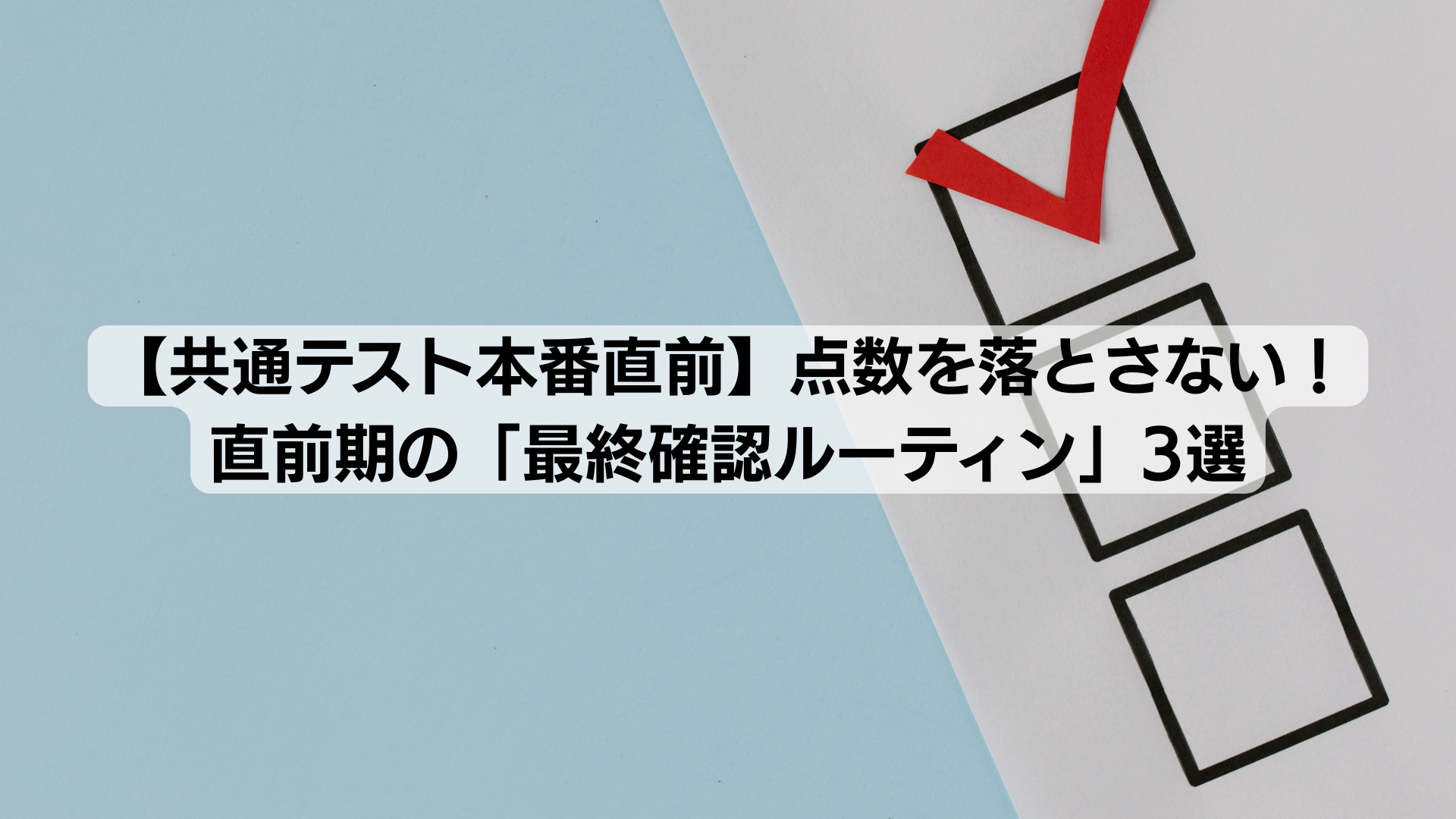模試の判定に一喜一憂しない!結果を「合格戦略」に変える3つの分析視点

はじめに:一喜一憂で終わらせない。「判定」は最高の情報源です
9月・10月は、模試の結果が続々と返却される時期です。
結果を見た瞬間、志望校のA〜E判定というアルファベットに、受験生も保護者の方も一喜一憂してしまいますよね。「D判定だった…このままじゃダメだ」と落ち込む受験生、「何と声をかけたらいいか分からない」と悩む保護者の方からのご相談が最も増える時期です。
しかし、立ち止まってください。
模試の「判定」は、今の学力を測るテストではなく、**「合格までの距離を示す地図」**です。この地図を正しく読み解き、戦略に変えることが、プロの仕事です。
今回は、我々個別指導のプロが、点数や判定から**「生徒の真の課題」を見つけ出し、合格戦略を立てるために見るべき3つの分析視点**を解説します。
視点1:成績表の裏側にある「大問別得点率」を読み解く
点数の合計や判定に目が行きがちですが、最も重要なのは**「どの分野で、どれだけ失点しているか」**です。
これは、あなたが**「真に苦手な分野」**を教えてくれます。
❌ 間違い:合計点を見て、すべてがダメだと諦める
「数学が全体的に低いから、数学を最初からやり直そう」と、広すぎる範囲に手をつけ、非効率な勉強に陥ります。
✅ プロの視点:失点パターンから「原因」を特定する
成績表の大問別得点率を見て、以下のパターンで課題を特定します。
- パターンA:特定の分野(例:数学の「ベクトル」)だけ、得点率が極端に低い
- 👉 戦略: その分野の基礎概念の理解ができていません。代ゼミの映像授業や、基礎問題集に戻って、すぐに穴埋めを行います。
- パターンB:どの分野も平均的に得点率が低いが、時間切れの設問が多い
- 👉 戦略: 処理速度と問題選定が課題です。基礎知識はあるが、試験時間内での運用力が不足しています。対策は解法暗記と過去問の時間配分です。
【個別指導の強み】 共通テスト形式なのか、記述形式なのか、出題形式に合わせて、今すぐ手を打つべき分野を特定できます。
視点2:「志望校内順位」と「合格者平均点」の差を埋める
判定がDやEでも焦る必要はありません。大切なのは、あなたが**「合格者平均点」**と比べてどのくらい不足しているか、という具体的な差です。
❌ 間違い:偏差値だけで「志望校を下げるべきか」と悩む
偏差値は全体の中での位置を示すものであり、志望校への合格可能性を示す唯一の指標ではありません。
✅ プロの視点:合格者平均点と「得点目標」の差を把握する
- ギャップの定量化: 志望校の合格者平均点が70%だとして、あなたの点数が50%であれば、**残り20%(約100点)**をどう埋めるかという具体的な目標設定ができます。
- 科目の優先順位設定: この100点を埋めるために、最も費用対効果が高い科目(例:伸びしろの大きい社会や、配点が高い英語など)に、残りの時間を集中投資します。
偏差値は気にせず、**「あと何点で合格ラインに到達するか」**という明確なゲームプランに切り替えましょう。
視点3:単なる「誤答」ではなく「思考プロセスの誤り」を分析する
模試の復習で、答えだけを見て「あ、計算ミスか」「知識が抜けてた」で終わるのは最も危険です。
プロの指導教官は、あなたの**「思考プロセス」**そのものをチェックします。
- 知識不足による誤答: 単語や公式を知らない。→ 対策: 暗記と基礎問題集の反復。
- 思考の誤りによる誤答: 知識はあるが、問題文の条件を見落とした、あるいは解答の手順を間違えた。→ 対策: 演習と復習時に**「なぜその思考を選んだのか」**を言語化する訓練。
特に、思考の誤りは自力で見つけるのが難しく、何度でも同じミスを繰り返します。これが、多くの受験生が「勉強しているのに成績が伸びない」と悩む原因です。
個別指導では、生徒が解いた痕跡(ノートや答案)から思考の癖を見抜き、正しい道筋を教えます。
まとめ:その不安を「上田予備校の個別戦略」で解消しませんか?
模試の結果は、落ち込むためのものではありません。合格のための地図です。
しかし、この地図を正確に読み解き、残り数ヶ月の最短ルートを設計するのは、自力では非常に困難です。ましてや、不安定になりがちな受験生本人が、冷静に分析するのは至難の業です。
我々、寺小屋義塾・上田予備校のプロ指導教官は、模試の成績表をあらゆる角度から徹底的に分析し、**生徒さん一人ひとりの「合格への最短戦略」**を立案します。
その第一歩として、まずは無料の個別受験戦略相談をご利用ください。
親御様からのご相談、お子様との三者でのご参加も大歓迎です。成績表を前に、不安を抱えるのは今日で終わりにしましょう。