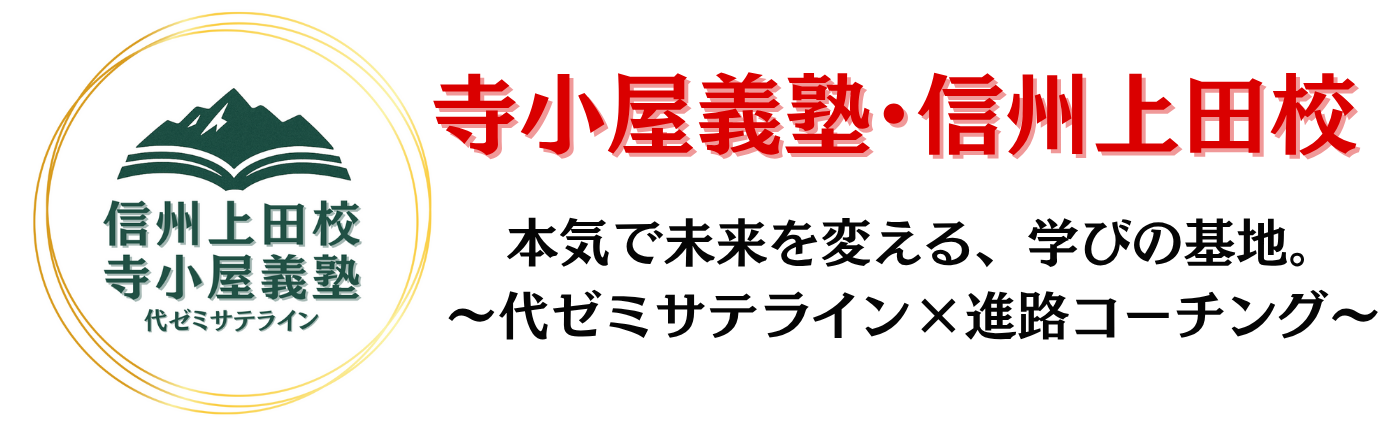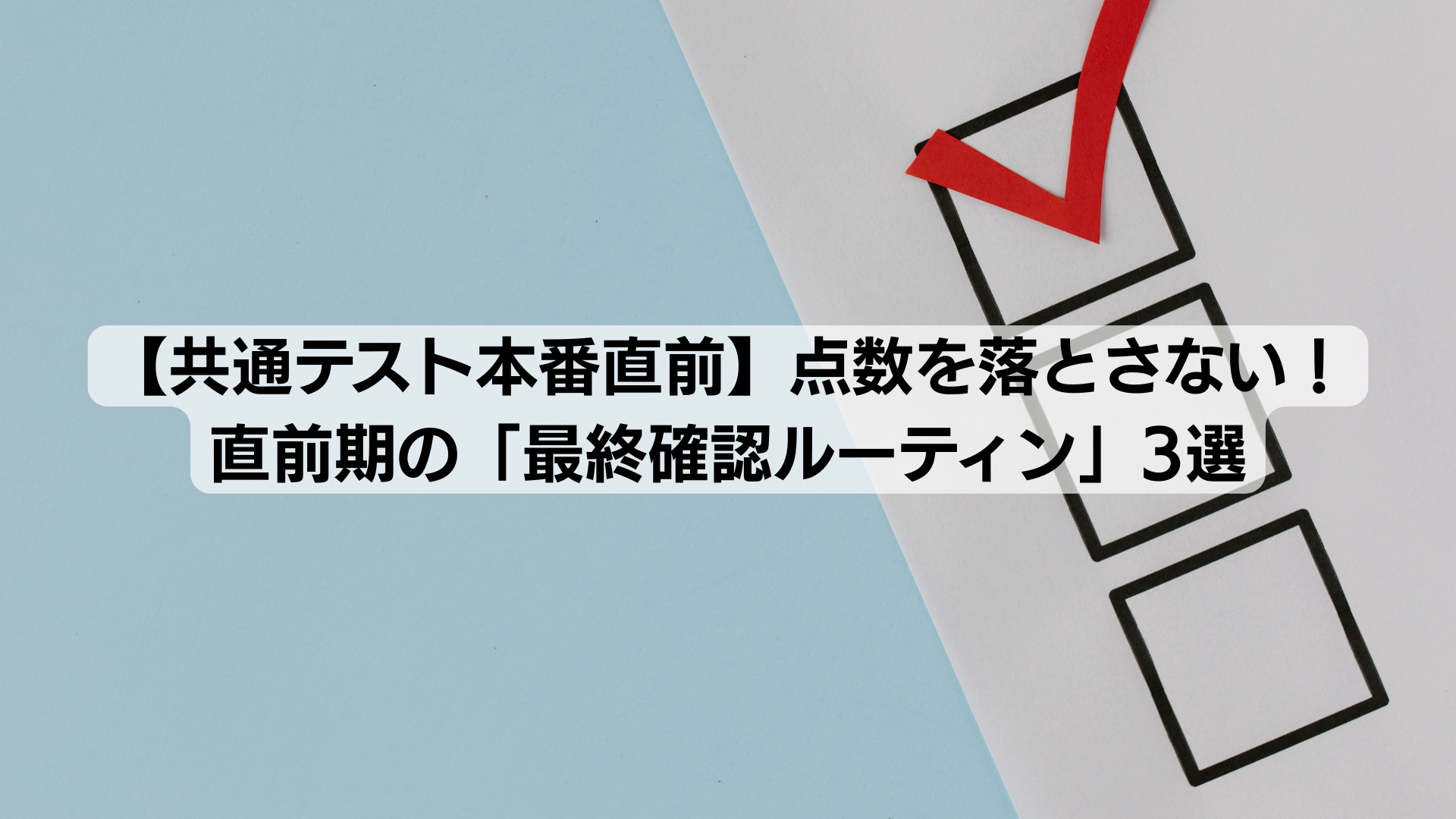【数学・理科】ただの公式暗記はもう古い!「知識を武器に変える」3ステップ学習戦略

1. 暗記偏重型の学習が、なぜ入試で通用しないのか
数学や理科の学習は、まず公式や基本原理を覚えることから始まります。しかし、最近の大学入試(特に共通テスト)では、単に公式を覚えているかを聞く問題はほとんど出ません。
問われるのは能力です。「覚えた知識を使いこなす能力」です。特に、初めて見る複雑な状況(問題文やグラフ)の中で、論理的に適用できるかが重要になります。したがって、知識を「覚えている状態」で留めてはいけません。自由自在に使いこなせる「武器に変わった状態」へレベルアップさせる必要があります。そのために、このレベルアップを意図的に行うための、寺小屋義塾が推奨する3ステップ戦略を解説します。
2. 知識を「武器」に変えるための3ステップ戦略
代ゼミサテラインの質の高い映像授業で「インプット」した知識を、確実に「得点力」に変えるための具体的なプロセスです。
ステップ①:「なぜ?」を深く掘り下げ、本質を理解する
公式や定理を見たとき、必ず問いかけを行ってください。「なぜこの公式が成り立つのか」。そして、「この概念の背後にある原理は何か」を深く掘り下げましょう。
- 実践方法:
- 公式をノートに書き出します。その際、公式が導かれる過程(証明)を意識してください。それを自分の言葉で簡潔に説明してみます。
- さらに、物理であれば、その現象が起こるイメージを頭の中で視覚化します。必ず図を書いてください。
- また、化学であれば、実験操作やグラフの意味を理解しましょう。それらを現象と結びつけることが大切です。このように、本質を理解することで、公式が変形された応用問題にも、柔軟に対応できるようになります。
ステップ②:解法の「思考プロセス」を記録・再現する
数学や理科の応用問題を解く上で最も重要なのは、思考の流れです。「どういう手順で、どの知識を使って解いたか」という流れです。具体的には、次の方法を試してください。
- 実践方法:
- 問題を解くときは、工夫が必要です。まず、「解答用紙」とは別に「思考記録ノート」を用意してください。
- 解きながら、プロセスを箇条書きでメモします。例えば、「まず〇〇の公式を使おうと考えた」「この情報から□□を仮定した」などと記録します。
- 間違えた問題はどうすべきでしょうか。講師の解説や解答を見ましょう。自分の思考プロセスとのズレを比較します。したがって、正しい手順を再現する練習をしてください。
その結果、入試本番で緊張していても、正しい手順で問題を解き進める力が養われます。
ステップ③:知識の「適用範囲」を広げる類題横展開
インプットした知識が「武器」として完成したかを確認するためには、訓練が必要です。知識の「適用範囲」を広げる訓練をしましょう。
- 実践方法:
- 代ゼミの授業で完璧に理解した問題をベースにします。そこから数字や設定が少し変わった「類題」を解いてみましょう。
- 例えば、物理であれば、「斜面」が「曲線」になった場合を想定します。このように条件を変えてみてください。
- これにより、実は、「この知識は、この範囲まで使える」という知識の境界線が明確になります。その結果、入試でどんな問題が出ても動じなくなるでしょう。
3. まとめ:戦略的な学習計画はプロの指導教官に相談を
数学・理科の学習は、「量」よりも「質」です。ただ手を動かすだけでなく、「どう考えたか」「どう使ったか」という戦略的な視点が必要となります。
しかし、一人で解決できない疑問も出てきます。「どの問題で類題横展開をすればいい?」「自分の思考記録が正しいか見てほしい」といった疑問です。さらに言えば、戦略的な学習計画はプロのサポートが不可欠です。
私たち寺小屋義塾の担当教官は、あなたを徹底的にサポートします。代ゼミサテラインの膨大な講座の中から、あなたの弱点克服と「思考力の強化」に最適な講座を選定します。そして、上記3ステップを日々の学習に組み込むための戦略的な学習管理を行います。
知識を暗記で終わらせず、入試本番で使える「最強の武器」に変え、私たちと一緒に合格を掴み取りましょう。
※担当教官は学習計画や進路に関する相談は行いますが、教科内容に関する質問対応(個別指導)はサービスに含まれません。