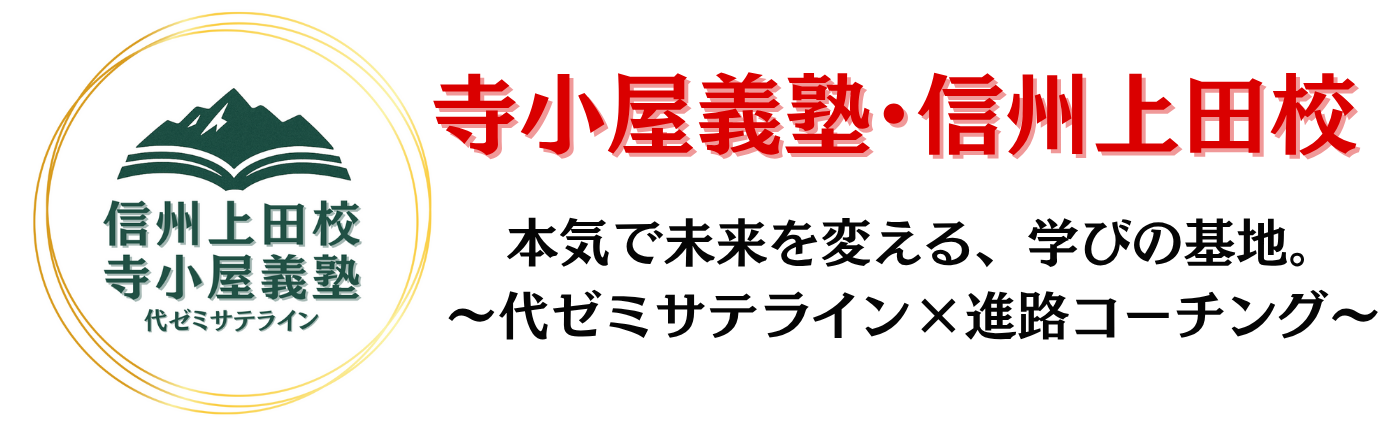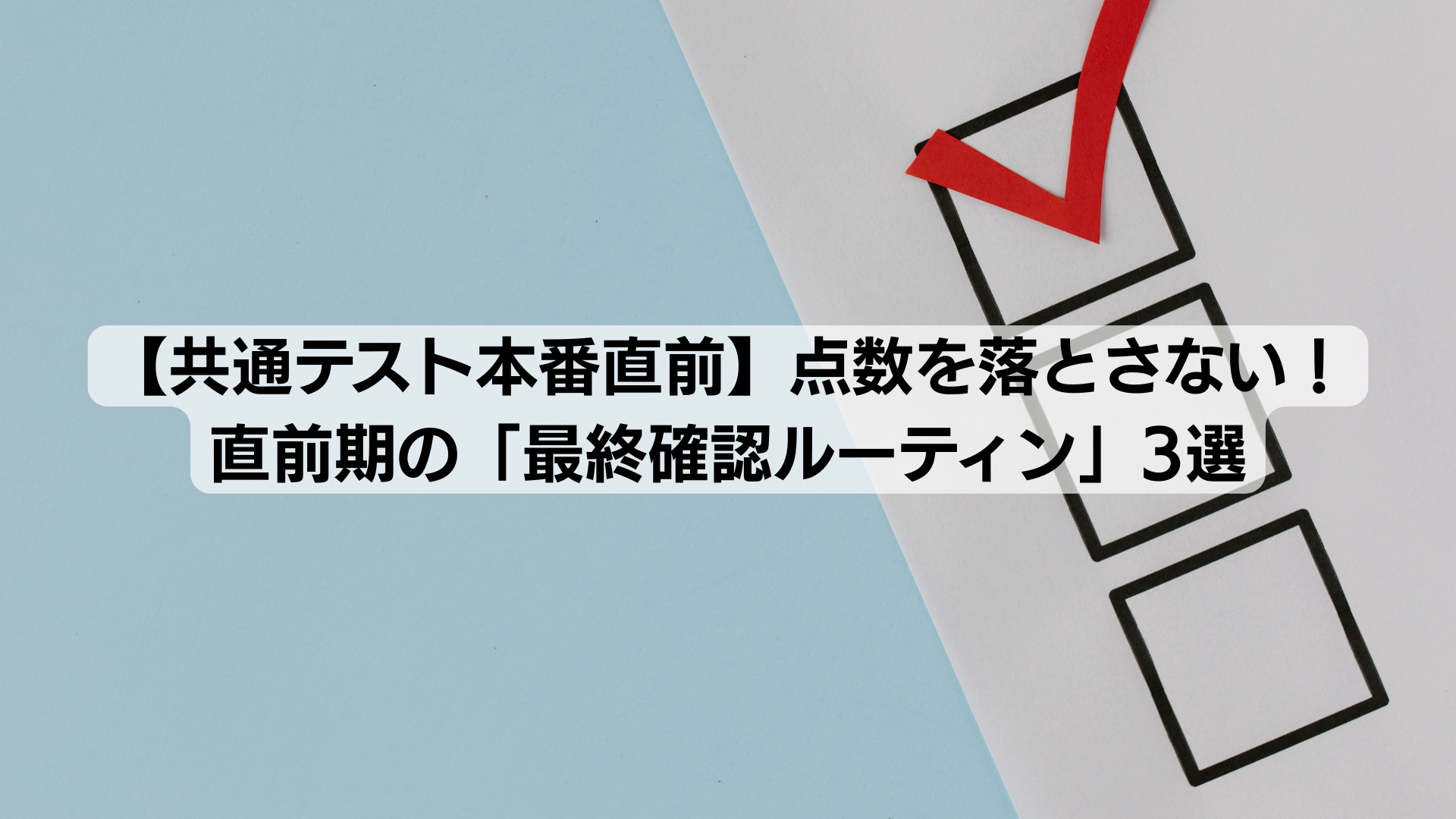【現代文・古文】フィーリングはもう卒業!代ゼミ授業で学ぶ1番の「論理的な解き方」

共通テストや二次試験の国語で、点数が安定しない最大の原因は何でしょうか?それは、「フィーリング」や「なんとなく」で文章を読んでしまっているからです。
代ゼミサテライン予備校には、文章を論理の構造体として読み解くための素晴らしい授業がたくさんあります。**しかし、**授業で「わかった」ことと、本番で「自力で解ける」ことの間には、大きな壁があります。
この壁を乗り越えるのが、私たち寺小屋義塾の役割です。ここでは、代ゼミの高品質なインプットを、あなたの安定した得点力に変えるための、具体的な「論理的解き方」の復習戦略を紹介します。

1. 【現代文】復習で意識すべき「構造把握」の3つの要素
現代文は、著者の主張がどこにあるか、それをどう補強しているかという論理構造で成り立っています。この構造を復習で再現できるようになることが目標です。
① 指示語・接続詞に「マーク」以上の意味を持たせる
代ゼミの授業では、必ず**指示語(これ、それ)や接続詞(しかし、したがって)**に印をつけます。**しかし、**復習で「ただマークする」だけで終わっていませんか?
- 復習の強化ポイント: 指示語が出てきたら、それが具体的に「どの文章の塊」を指しているかを、自分の言葉で本文の余白にメモしましょう。**なぜなら、これこそが、筆者の主張と設問の答えを正確に結びつける「論理の線」**だからです。
② 問題の「正解」ではなく「不正解の理由」を分析する
現代文の設問は、正解を選ぶゲームではなく、明確な論理的な間違いを含む選択肢を消去するゲームです。
- 復習の強化ポイント: 正解した問題も含め、間違った選択肢A〜Dが「本文のどこ」と矛盾しているのかを特定します。つまり、「なんとなく違う」ではなく、「本文○行目の記述と食い違っているから間違い」という論拠を言語化する練習をしましょう。
③ 「主張」と「具体例」を色分けする
筆者の言いたいこと(抽象論)と、それを分かりやすく説明している部分(具体例)を分離する訓練をします。
- 復習の強化ポイント: 主張には青ペン、具体例には赤ペンで線を引き、その段落で筆者が本当に言いたいことがどこにあるのかを明確にします。**その結果、**設問に問われやすい「主張」が、具体例の表現に惑わされることなく、一瞬で見抜けるようになります。
2. 【古文】フィーリングを排除する「知識の武器化」戦略
古文の読解は、現代文と異なり**「知識の正確さ」**が解法のベースになります。「なんとなく」で訳す余地は一切ありません。
① 「最重要単語」の意味を文脈で確定させる
古文単語は多義語が多いため、単語帳通りの意味が通用しないことがあります。
- 復習の強化ポイント: 授業で出てきた多義語をノートに書き出し、その単語が**「本文でどういう状況で使われ、どう訳されたか」という文脈情報をセットで記録します。たとえば、「おぼろけなり」を「並一通りではない」と覚えるだけでなく、「並一通りではない(=格別だ)」という訳が、その文の主語(身分の高い人か否か)**によってどう変化するかを意識しましょう。
② 敬語の「方向性」を可視化する
敬語の把握は、登場人物の関係性を理解する上で極めて重要です。
- 復習の強化ポイント: 敬語表現が出てきたら、**「誰から(話し手・書き手)」「誰へ(動作の対象)」**という矢印を本文に書き込みます。したがって、この矢印を把握することで、誰が誰に話しているのかという人間関係の構造が論理的に確定し、登場人物の特定ミスを防げます。
まとめ:論理の武器で国語を安定させる
国語は、決して才能やセンスで決まる科目ではありません。
現代文では構造把握と論拠の明確化を。古文では知識の正確な文脈適用を、復習で徹底してください。
私たち担当教官は、代ゼミの授業で得た知識が、あなたの**「論理的な解き方」**として定着しているか、復習ノートや模試の結果を通じて定期的にチェックします。
このように、「なぜ正解したか」「なぜ間違えたか」を論理的に説明できる状態こそが、国語の点数が安定するゴールです。
▼【国語の解き方を論理的に確立】無料受験戦略相談に申し込む (あなたの弱点に合わせた復習計画を教官が一緒に設計します) [相談フォームはこちら]