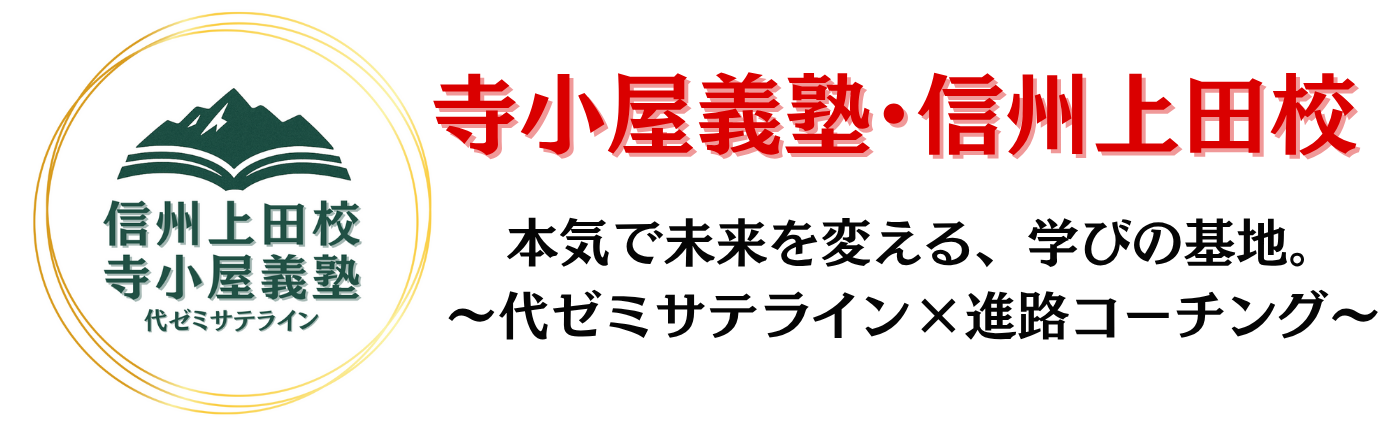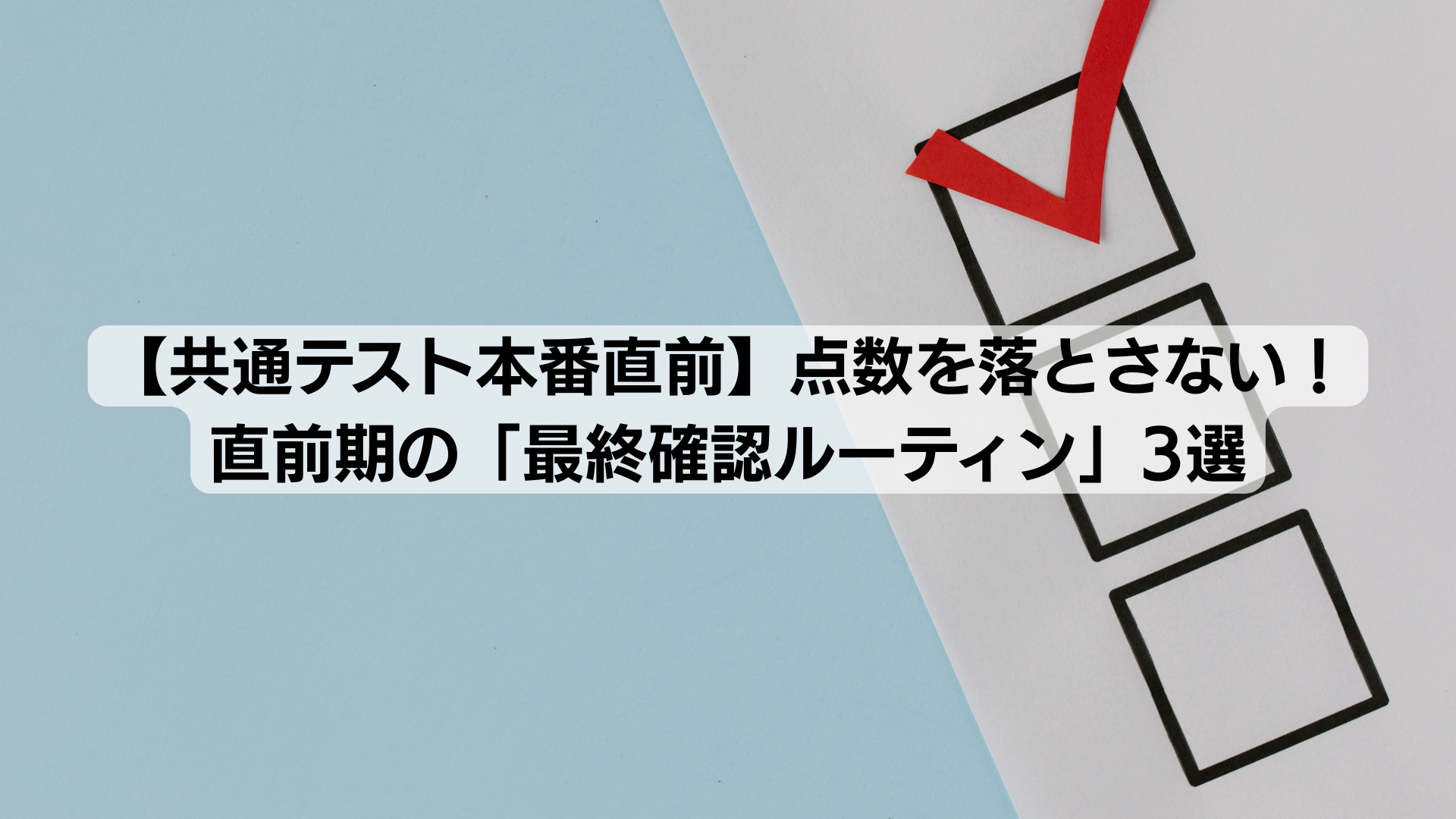親子で乗り越える受験の壁!「見守る」と「干渉する」の境界線

1. なぜ「干渉」したくなるのか?―その気持ち、痛いほどわかります
受験期のお子さんを持つ保護者の方にとって、不安な気持ちは尽きないものです。
「本当に勉強しているのだろうか…」 「志望校のレベルは、これで大丈夫だろうか…」
こうした不安から、ついつい「勉強しなさい」「ちゃんと計画通りに進んでいるの?」と口を出してしまう。これは、お子さんへの愛情と心配から来る自然な感情です。プロの指導教官として、そのお気持ちは痛いほどよくわかります。
しかし、過度な「干渉」は、時にお子さんの自主性ややる気を奪い、かえって逆効果になってしまうことがあります。では、どのように接すればよいのでしょうか。
2. 「干渉」と「見守り」の違いを知る
ここで、受験を成功させるための親子の関係における「干渉」と「見守り」の違いを明確にしましょう。
| 「干渉」 | 「見守り」」 | |
|---|---|---|
| 主な行動 | ・「勉強しなさい」と指示する ・テストの点数を過度に追及する ・お子さんの行動を常に監視する | ・「何か困っていることはない?」と問いかける ・話を聞く姿勢を見せる ・頑張りを褒め、労いの言葉をかける |
| お子さんの心理 | ・「信じてもらえていない」と感じる ・反発心やプレッシャーを感じる ・自主的に動く力が失われる | ・「味方でいてくれる」と安心する ・「頑張ろう」と前向きな気持ちになる ・自律的に行動する力が育つ |
受験期は、お子さんが自立に向かう大切な時期です。親がすべてを管理する「干渉」から、お子さんの成長をサポートする「見守り」へとシフトすることで、信頼関係はより強固になります。
3. 今すぐできる!「見守り」の具体的なアクション
では、具体的にどのような行動が「見守り」に繋がるのでしょうか。
- アクション①:体調管理のプロになる
- 栄養のある食事、十分な睡眠時間、リフレッシュできる環境を整えてあげましょう。「今日も頑張ったね」と労いの言葉をかけるだけでも、お子さんにとっては大きな支えになります。
- アクション②:相談相手に徹する
- 勉強の内容に踏み込むのではなく、「今日は学校でどうだった?」「最近、何か悩みはない?」と、日常の会話を大切にしましょう。お子さんが話したい時に、いつでも聞く準備ができていることを示してください。
- アクション③:外部のプロを頼る
- 勉強方法や進路の悩みは、無理に親だけで解決しようとせず、予備校の講師などプロに任せることも大切です。寺小屋義塾の個別面談は、お子さんの学習計画だけでなく、メンタルサポートも視野に入れたものです。
受験は、お子さんだけでなく、ご家族全体のチーム戦です。お子さんを信じ、そっと背中を押してあげる「見守る力」が、合格への大きな原動力となります。
寺小屋義塾では、お子さん一人ひとりの状況に合わせた学習指導はもちろん、保護者の方のご相談にもお応えしています。いつでもお気軽にご連絡ください。
TAG