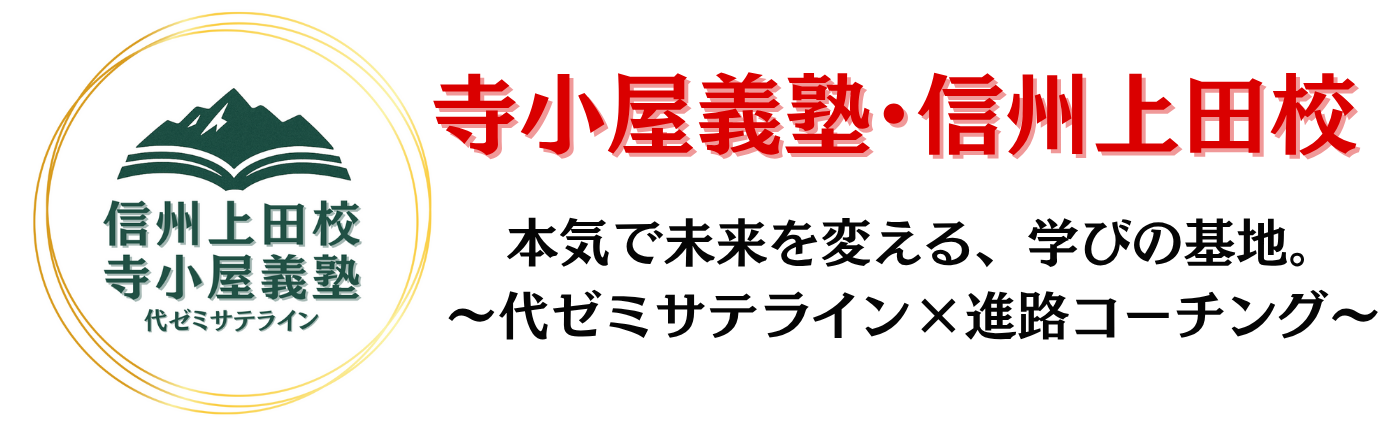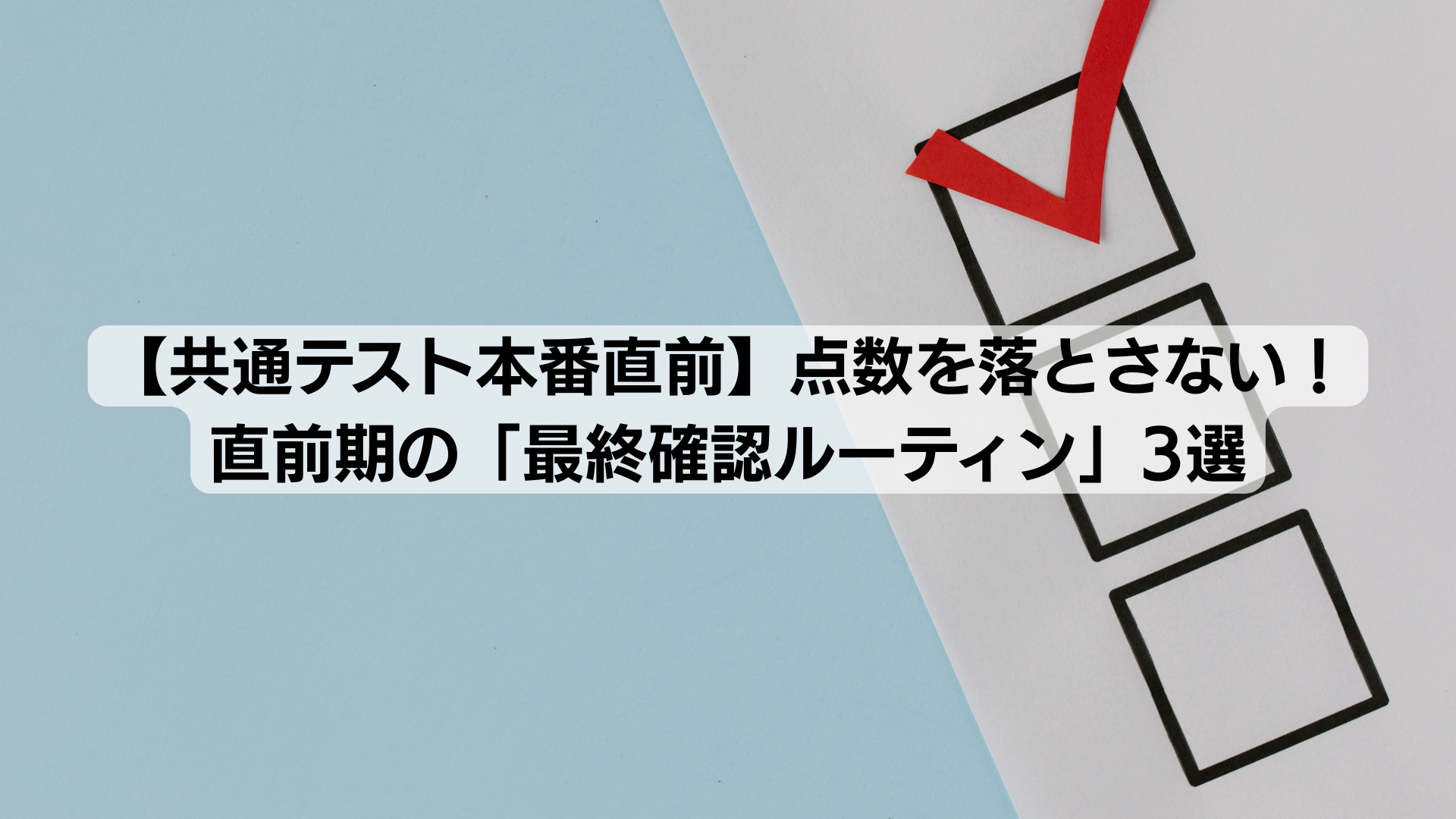【理系必見】共通テスト「物理・化学・生物」で満点を狙う!出題傾向と学習戦略

共通テストの理科は、旧センター試験に比べて**「思考力」「判断力」「表現力」**を問う問題が増加しています。単なる知識の暗記だけでは通用せず、教科の根本的な理解が不可欠です。
ここでは、それぞれの科目の出題傾向と、高得点を取るための具体的な学習戦略を解説します。
1. 物理:基本法則の「理解」が鍵
共通テストの物理は、日常生活や身近な現象を題材にした問題が多く出題されます。
出題傾向
- グラフや実験データから法則を読み解く問題が増加。
- 複数の単元を組み合わせた融合問題が頻出。
- 物理法則を言葉で説明させる問題も出題される。
学習戦略
- 公式を覚えるだけでなく、**「なぜその公式が成り立つのか」**を理解する。
- 教科書や参考書で、基本法則や原理を丁寧に復習する。
- 過去問や問題集で、グラフや実験データを読み解く練習を徹底的に行う。
2. 化学:分野間の「関連性」を意識する
化学は、理論化学、無機化学、有機化学の3つの分野からバランス良く出題されます。
出題傾向
- 実験操作や化学反応の仕組みを問う問題が多い。
- 計算問題は、有効数字や単位に注意が必要。
- 複数の分野を横断する複合問題が頻出。
学習戦略
- 各分野の知識を単体で覚えるのではなく、**「理論→無機→有機」**のように、分野間の関連性を意識して学習する。
- 教科書に出てくる代表的な実験は、その目的や操作方法を理解しておく。
- 化学反応式は、**「書ける」だけでなく「意味がわかる」**レベルまで練習する。
3. 生物:知識と「応用力」を鍛える
生物は、膨大な知識量が必要ですが、共通テストではその知識をどう使うかが問われます。
出題傾向
- グラフや表の読み取り、実験考察が中心。
- 生物の多様性、生態系、遺伝子など、最新の研究動向を踏まえた問題も出題される。
学習戦略
- 教科書に出てくる専門用語は、その意味を正確に理解し、人に説明できるレベルまで覚える。
- 過去問や問題集の実験考察問題を繰り返し解き、知識を応用する力を養う。
- 日頃から、科学ニュースや生物学に関する記事を読む習慣をつける。
まとめ:本物の「理科力」を身につけよう
共通テストの理科は、表面的な知識だけでは太刀打ちできません。
**「なぜ?」という疑問を大切にし、「理科の本質」**を理解する学習が不可欠です。
寺小屋義塾では、生徒一人ひとりの「なぜ?」に寄り添い、理科の本質を理解するための指導を行っています。
一人で悩まず、ぜひ私たちに相談してください。
TAG